僕は早起きが嫌いだ。「早起きは三文の徳」といわれても、「たかが三文(現代では100円程度)しかメリットがないなら、遅くまで寝ていたい」と考える。早起きすると、体調が悪くなることも多い。
しかし、旅先では早起きする。朝6時前には起床して、宿泊先の周辺を散歩する。2025年8月26日の早朝も、僕は早起きして式根島の南東を散歩した。宿泊先の民宿「ふるさと」を朝6時に出発し、前日友人に案内してもらった温泉へ。その途中、観光MAPに載っている場所にも載っていない場所にも立ち寄った。
式根本道の祠
式根島の主要道路である式根本道を南西に進んで行くと、スーパーマーケット「おくやま」やレンタサイクルステーション「まんぼう」などが見えてくる。おくやまの前には掲示板、郵便ポスト、公衆電話が並んでいて、この公衆電話の横の、少し奥まったところに祠がある。


祠はひっそり存在しているので、観光客の多くはその存在にすら気づかないだろう。しかし、祠の前に「本醸造 喜平」が供えられているのを見る限り、地元の人たちには大切にされているようだ。
案内板などがないため、祠が何の目的で建立されたのか、また、何が祀られているのかは不明。
モヤイ像・水神社
謎の祠から南へ進むと十字路がある。ここで左手側に曲がり、式根島のお土産を販売する「いのうえみやげ店」の前を通って、丁字路を左手側に曲がる。ここで視界に飛び込んでくるのが、木々の間に佇む石像。

これは、お隣の新島で産出されるコーガ石に掘られた「モヤイ像」だ。イースター島のモアイ像のパクリと考えられがちだが、実は「モヤイ」は「助け合い」を意味する新島の言葉。助け合いの象徴として、式根島にもモヤイ像が存在するという。
モヤイ像の背後の広場には祠がある。


この祠についても案内板などがないため、散歩しているときは「謎の祠」という認識だった。後日ネットで調べたところ、「八百万の神 – 日本の神社・寺院検索サイト」で「水神社(すいじんしゃ)」として紹介されている。
水神は、その名の通り、水に関係する神様。式根島は長年、水不足に悩まされてきた経緯がある。祠のすぐ近くにまいまいず井戸もある。だから、祠の祀神が「水神」として紹介されているのだろうが、その真偽は不明。結局、「謎の祠」であることに変わりはない。
式根島まいまいず井戸
水神社のある広場の隣には、式根島まいまいず井戸がある。
「まいまいず」とは「かたつむり」の意味。井戸へ降りる通路がかたつむりの殻のように螺旋状なので「まいまいず井戸」と呼ばれる。同じ構造の井戸は東京都多摩北部地域から埼玉県西部に多く、八丈島の「メットウ井戸」や新島の「原町井戸」などもその仲間だ。
式根島まいまいず井戸は、明治23年(1888年)から同25年にかけて作られた。この井戸を中心に集落が形成され、島民の生活と産業経済が大きく向上した。


案内板が「まいまいず」ではなく「まいまず」になっているのはご愛敬。キモかわいい「しきねいぬわし」のイラストもちょっと気になる。
開島50年記念碑
式根島まいまいず井戸の正面には開島50年記念碑がある。

式根島は、吹之江遺跡(ヘリポート)や石白川遺跡などから縄文時代中期の遺物が大量に発掘されたことから、紀元前6500年頃には人が住んでいたと考えられている。しかし、江戸時代には定住者がいない無人島だった。新島から4世帯8人が移住して開島したのは明治21年(1886年)。この年から50年後の昭和11年(1936年)、島の中心地である式根島まいまいず井戸の前に記念碑が建てられた。
記念碑は木々に囲まれているので、僕は最初、気づかずに通り過ぎてしまった。観光MAPを確認して道を戻り、写真を撮った。この後、十字路で南の坂道を選んで下って行った。
朝6時台の式根島は、外に出ている人がほとんどいないので、朝日を浴びて輝く景色を独り占めできる。誰にはばかることなく写真を撮れる。早朝散歩は旅の醍醐味だ。
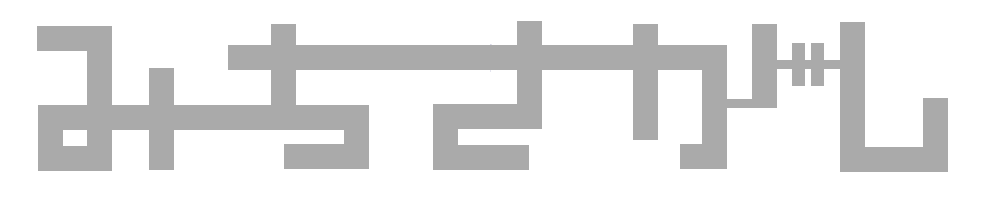

コメント